
 HOMEへ戻る
HOMEへ戻る
1929年出版のイギリスの蓄音機と電気式アンプの最良の本として、日本でも多くの権威者が参考にした本の内容を紹介して行こうと思っています。私は見たことがないのですが、日本でも別の著者の名で出版されたことがあるそうです。すでに抄訳は2000年9月より2002年4月に渡って、ラジオ技術誌で連載されております。取りあえず、各章のまとめ、あるいはいくつかのトピックを拾って、ここでも簡単に発表しておきます。
取りあえず、第2章の内の一つのセクション辺りが面白いかも知れません。初期の録音がいかに大変だったかが書かれています。
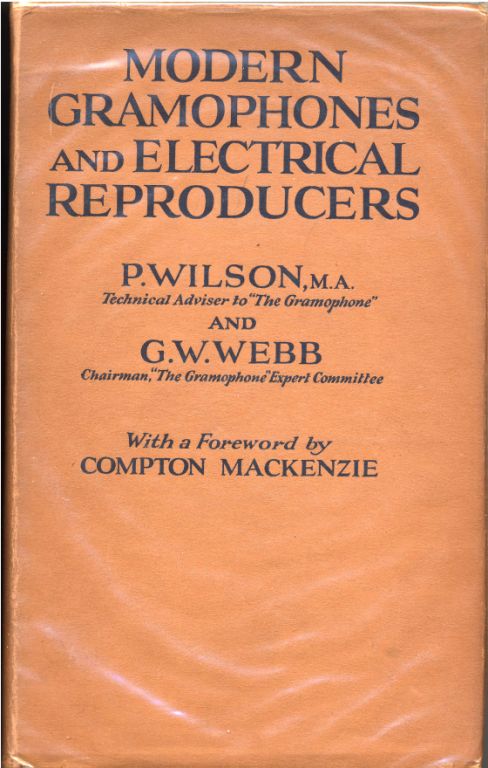 1929年に英国で出版された、「Modern Gramophones and Electrical
Reproducers」の目次と、その内容を少しずつ紹介します。
1929年に英国で出版された、「Modern Gramophones and Electrical
Reproducers」の目次と、その内容を少しずつ紹介します。
0. PREFACE
著者たちによる前書き
1876年にBellによって電話が発明され、翌年の1877年にはEdisonがトーキング・マシンを発明した。その後、音の再生技術は機械式と電気式の2つの流れが独立して発展した。19世紀が終わるまでの20年間、エジソン(蝋管式蓄音機)、
ベル(電話)、 テインター(グラフォフォンの開発)、 ベルリーナ(円盤式蓄音機)、 エルドリッジ R. ジョンソン(実用機蓄音機の開発)、 H. ジョーンズ、
ヘンリー・セイモア
やその他の開拓者が録音再生に取り組んできた。しかしその後の25年間は技術的な進歩は殆どなかった。しかし、音楽家や大衆に録音再生機械というものを認めてもらう大切な期間だったようだ。
一方、電気の基礎研究の方は、J.
J. トムソン(電磁気学)、 マルコーニ(無線)、 フレミング(発電の原理、2極管)、 ド・フォレスト(3極管)、 リチャードソン、 G. A.
キャンベル(電話伝送、フィルター)、
ウェブスターなどによる研究がこの期間大いに成果を上げてきた。そして1925年、2つの流れが一緒になり、技術的にも、商業的にも大きく飛躍するきっかけとなった。
実用的な進歩の中で最高のものは、電気式録音システムにある。この分野の発進歩にはさらなる利点があった。それは、電気のインピーダンス理論を、機械理論に応用することである。これは、大変複雑な問題を簡易化して、回答を得るのに大いに役立ったからである。長期的に見ても、このような技術の進展は以降の発展を促すのである。
この本では新理論の入門書としての解説を行った。取り上げる項目の多くは、過去20年くらいのグラモフォンに関する実際の経験から来ているが、掲載する際や、理論的解説には、大量の実験を元にした、ここ5-6年の研究成果を使っている。そして、この期間に、職人技が科学に変わったのである。
著者たちは、原理はよく解明されたので、次に進む方向ははっきりと見通せるようになったと信じている。開発のスピードが上がり、特に電気式再生の分野は著しい。だから、グラモフォンやフォノグラフよりも優れた機械が近い将来現れるのは間違いない。この本は、一般の人で最近の進歩の背景を理解したい方々や、またこの技術分野で働いている方も対象にしている。だから、数式を避けるわけには行かなかった。ただし、なるべく付録で解説し、本文の文章には入れることはなるべく避けた。今まで科学論文誌などに出る記事は録音再生技術の一部分のみであることが多く、全体像をバランスよくまとめたのは本書が最初であると思う。
1. Sounds and
Sound-Waves
Sound
Waves
Wave
Front
Velocity, Wave-length,
Frequency, Amplitude
Simple
and Complex Waves;
Phase
Analysis of
Sounds
Musical
Sounds
Transients
Sensitivity
of the Ear
Requirements for
Perfect
Reproduction
Permissible
Errors in Reproduction
楽器の音
楽器の音とサイン波の要素との関係は、比較的に単純で密接である。つまり、構成音は整数倍の関係がある。音質はある倍音がないとか、強さが違うとかで変わってくる。周波数が2倍の音は、オクターブ。3倍の周波数は12番目(トェレフス)、4倍はダブル・オクターブと言う。構成音の周波数が一番低いものが基音と呼ばれ、それが音程を決めている。可聴周波数については、人によって定義が違うが、16サイクルから16,000サイクル(Hzのこと)までである。音楽における基音の上限は5,000サイクルを越えることはない。人間の声では、バスの下限が60サイクル、ソプラノの上限が1,300サイクルである。声や楽器の倍音は10,000サイクル以上に広がっている。
註:日本では1972年より、周波数をヘルツ(Hz) で表すようになったが、以前は毎秒あたりの振動数、サイクルで表していた。
トランジェント音
基音の整数倍の構成音のない楽器がある。それは主に打楽器である。ドラム、シンバル、トライアングル、それにピアノが含まれる。周波数成分は調和していないので、再生が非常に難しい。音質は、他の楽器と同様な倍音関係にもよるが、音の振幅が減少し始めるまでの期間と構成音の位相関係にもよる。 そして、必要でないトランジェント音も出てしまうことが多い。不要音が長すぎれば、再生音がぼけてしまう。
耳の感度
大戦後(1914~18年に行われた第一次世界大戦後のこと)、様々な音波を使って、耳の感度の研究をすることが盛んに行われてきた。耳の特徴は、基音を再現する能力である。この能力により、人工の再生音で起きがちの低域の不足が補えるのである。そうでなければ、音程が狂って聞こえることになり、再生は破滅的なことになってしまう。耳は周波数の変化であれば、わずか0.3%の違いを見分けるが、音量となると10%位の違いが分からない。特に可聴限界に近い小さい音では、30%の差がないと分からないくらいである。また、最低可聴音は周波数により異なり、もっともエネルギーが低くても聞こえるのは、2,000-4,000サイクルである。32サイクルの音の最低可聴音量のエネルギーは、1,000サイクルの音の100万倍、2000サイクルの音の1,000万倍も必要である。また、音量が増えてくると、音を聴くと言うより、むずむずしたり、苦痛になったりするようになる。つまり聴くのではなく、感じるようになるのである。
常用対数の10倍を取った単位をT.U.(伝送単位:トランスミッション・ユニット)と決めると、音量差が分かるレベル差は、0.5あるいは1.0となる。バスの低い方が音のボディーとなり自然さ、パワーとなる。また高音は音の明瞭度を決める。音のエネルギーは256サイクルより下側に集中し、3000サイクルまで急速に減る。また、音の明瞭度として大事なのは1000サイクル付近と5000サイクル付近である。音声では、自然さはなくなるものの500から2,000サイクルまであればよい。自然な感じにするには少なくとも100から3,000サイクルまで必要である。高音側を伸ばしていくと、さらに音質が改善されるのである。
完全な再生に必要なもの
完全な再生音というものは、元の音と区別ができないような再生音ができることである。つまり、音楽ホールの最高の席に座って聴く音楽の様々な特徴が、レコードを聴いたときに再現できることができればよいだろう理想的には、ホールで各楽器の強さまで、再現できればよいのだろうが、ある範囲内であれば許容できる。元の音より強ければひどい音になる。すごく弱い場合も歪みが出るが、これはオリジナルを遠くで聴いたとすれば許容できる。可聴限界以下の構成音があると音が薄っぺらになる。特に低音の再生をきちんとするのはいつも難しい。再生音は、録音装置と再生装置が、総合的に働いた結果である。録音装置の品質に比べ、再生装置は一般的にはよくない。だから、リプロデューサー(サウンド・ボックス)で拾う振動は歪みがないようにしなければならない。
次に、再生音の構成音の強さの比は、どの周波数でも元の音楽の比になっていなければならない。そうでなければ周波数歪みが起きる。
現実の装置の応答性には特定の偏りがある。それは共振があるからである。現状では、再生装置の周波数特性は50から6,000サイクルを越えることはないが、実用上は問題がない。次に、小入力での再生音と、大入力での再生音がリニアでない場合、振幅歪みが起きている。さらに、オリジナルに含まれていない、構成音が出る場合もある。次に音楽の1音の長さが実際により長くなると、音がぼけて、特にトランジェント音は相当に影響されてしまう。だからピアノの音の再生は非常に難しいのである。トランジェント音の音質は位相がずれることにも弱いが、これは分析が難しいので、今後の研究課題である。
2. Record and Recording Systems
Production of
Mechanical Vibrations
Early
Recording ystems
Ideal
Respoonse to Sound
Resonance
and Damping
Electriccal
Recording
Electrical and
Mechanical Analogies
The
Electromagnetic
Recorder
Lateral-cut and
Hill-and-Dale
Records
Appendix.-Note on
Electrical Circuits
第2章の内の一つのセクションの抄訳を載せておきます。初期の録音がいかに大変だったかの説明です。それと全体のまとめを簡単に書きました。
初期の録音システム
1925年まで、商業的に行われる録音システムは多くの改良があったとはいえ、基本的に同じ原理であった。(ホーンの)喉の部分にダイアフラムを取り付けたコニカル型ホーンが一般的に使われた。初期には音楽の種類によって、ダイアフラムの材質や口径を変えたりしたが、結局は薄いガラス板に落ち着いた。ホーンの目的は広い範囲の空気振動を集めて、ダイアフラムに対し高めた圧力を加えることである。音楽家の要求によっては、4つのホーンを1つのダイアフラムに対し使用することもある。ダイアフラムの裏側には針が取り付けられており、その下で回転しているソフトワックスのシリンダーあるいはディスクに刻み込んでいく。機械式の録音では、根本的な問題が解決できていない。一番の問題は、レコードをカッティングするためのエネルギーがあまりにも小さいことである。ホーンやダイアフラムをいくら工夫しても限界がある。ホーンの周りに音楽家が集まるのだが、場所が狭すぎる。小さな音の楽器は大きな音がするように改造したり、ホーンの直近に移動させたり、また大きすぎる音の楽器は遠くに置くか、使用をあきらめる。また、フル・オーケストラのように大きな場所が必要な演奏は事実上不可能である。大事な楽器だけ残した骨組みのようなオーケストラを編成しても、問題は多い。演奏する環境は最悪で、スタジオはすごく暑くなる。歌手はそれよりましな空間がもらえるが、頭を少しでも動かすと、録音した音が悪くなるので動かせない状態である。アコースティック録音(この呼び名はなぜか正確でない名だが)における問題は、ホーン、ダイアフラム、カッティング針が起こす深刻な歪みである。
第2章のまとめ
相当精緻に機械式の限界、電気式の現状と将来の方向など解説されており、その見通しが正確であることに驚かされます。つまり機械式では、どうしてもフラットな周波数特性が得られないことと、低域・高域録音の限界があること。それを解消するために電気録音が電話技術の応用として登場したこと。実際のレコードのカッティングに使う録音特性についての詳細を論じています。また、マイクと一種の特性補正アンプをホールに持ち込んで、電話線を通じて演奏会場と、録音システムと長距離伝送をし、カッティングする技術など面白い発想です。また、電気吹き込みがダイレクトカットのみであったところから、フィルム上に録音することも予測されています。これは1960年ころMercuryなどで行われた35mm映画フィルムをベースに録音したハイファイ録音で花開いた技術です。CDで復刻されたものを聴くと、そのころのハイファイ録音のレベルの高さが実感されます。技術開発では如何にものを見通す力が必要か。そのための実験と結果の解析、数学の応用、理論化しておくことなど、精神主義では決して得られないしっかりとした基礎を作り上げていると思います。実際、数十年以上、いや現在でも通じる話をしているのではないでしょうか。いかに電子回路や素子が発達しても、当分スピーカーというメカニカルな部品が残るでしょうから。
3. Reproducing
Systems
Historical
Summary
The Scientific
Stage
Even
Response
Limitations of
Mechanical
Reproduction
Electrical
Reproduction
Advantage of
Electrical Reproduction
科学的な時代
この期間、蓄音機のデザインは純粋に、経験主義であった。相当な数の実験者が、多くの関連性のない結果を集めた。多くの結果は一見矛盾しているように見え、統一性のある理論はなかった。このような環境では、開発がいずれ壁に当たるのは見えている。経験主義は限界に達し、科学的な考え方という刺激が必要になるのだ。戦後(註:第一次大戦!)雨後の竹の子のように多くの新興蓄音機メーカーが起こり、それぞれが完璧な再生音を売り物にした。しかし、これらの主張はちょっと調べればすぐに崩れるようなものだった。ある特長を改善するというとき、例えばスイートな音と言えば、解像度や鮮明度を犠牲にするしかないのであるから。過去を振り返って、蓄音機業界の技術エキスパートが確実な設計基準をそれほど長い間、作れなかったことは少し理解できないことがある。ダイアフラムの動作理論はだいぶ以前から分かっていたし、ホーンの理論要素はRayleigh卿が70年代初期に発表されていた。1919年にはWebsterが米国全米アカデミーの報告書でRayleigh卿のホーン理論を多く引用し、その上特定のホーンに関しては、特性を詳細に検討した。実際の再生向けとしては最も成功した仕事と受け取られている。しかしWebsterの仕事は1923年にWestinghouse電気会社のHannaとSlepina博士が米国電気技師協会の前で再生用ホーンの機能と設計について徹底的に議論した論文を発表するまであまり知られなかった。ある部分は完全ではなく、それ以外は単にWebsterの要約でしかなかった論文によって、蓄音機開発の理論的発展の出発点となった。それまでは、理論がなかったが為に、蓄音機の発展が停止していたのである。そのころ、電気録音を開発したMaxfieldとHarrisonなどのBell電話研究所のエンジニアは、電気伝送理論を機械音響振動での似たような問題に対し応用した。今まで経験的に行われていた、サウンド・ボックスとホーンの標準設計は、電気波形フィルターの構造と正確に一致している。また、波形フィルター理論のアナロジーを適用する事で、電話のエンジニアが蓄音機の動作の定性的、定量的な測定をすることが可能となった。これらのエンジニアの仕事が蓄音機技術の新しい方向と言えないまでも推進力となった。この種の開発以降の数年間は、集中して研究、それぞれのステージの理論の再検討が行われ、多くの工夫が出来、もっと重要なことには、理論を実際に近づけるためのより良い方法を発見することだ。一つには研究所の機械を製作し、理想を満足させることで、もう一つは実際の市販品製造部品を標準化することである。研究所では、コストや時間を考慮せずに、細かい注意を与えることもできるし、特別の調整もできる。ところが、工場では、部品は標準化しておき、組立方法は経験の深さを考えて決めなければならない。製造コストを十分下げておくためには、製造する重要部品の精密な調整が必要にならないようにしなければならない。それでもよい音を再生するには、蓄音機ユーザーが再生装置の部品の動きについて学んでおき、調整方法を知っておかなければ、得られないだろう。この新しい大地からの果実をすべてとることをすぐに期待してはいけない。ただ、最初の実であっても、決して食えないわけではない。1926年以降に設計された蓄音機は、確かにそれ以前の物より優れている。実際、再生装置の応答特性を見ると、低音、高音、ピークが改善されている。それは共振が相当に減ったからである。つまり、帯域が広がり、その帯域がフラットになった。
フラットな周波数特性
レコードで、定速録音システムをしたものは、サウンド・ボックスが均一な応答をすれば、完璧な再生が出来る。人間の耳の感度特性はとても均一な応答とは言えないお陰で、よほどの違いがあるなら別だが、少々均一でない特性でも許される。応答特性のグラフ(図3d)はとても完璧とは言えない。ピークや谷間がおびただしくある。ただし、よく見るとその差は5T.U.以内である。だから、目で見るとギザギザだが、耳で聴くとそれほどの誤差でもない。例外は130サイクルの谷間と、600から800サイクルのピークだ。それらの開きは14T.U.に達する。それでも、この機械の応答はそれ以前の市販の製品と比べれば、疑問の余地なく優れている。
それでも、応答に関して見落としてはいけない重要な点がある。つまり、再生はどんなに頑張っても録音時よりよいことはない。第二章で説明したが、物理的な限界により、録音時に300サイクル以下と、約5,000サイクル以上の応答を落としているのだ。だから平らな応答特性があるレコードの再生とは、300サイクル以下と、5,000サイクル以上では不完全なものである。もしフラットな応答を可能とするには、300サイクルと5,000サイクルの間は平らで、なおかつその外側の周波数帯で音量を強調しなければならない。
しかしながら、メカニカル再生機では、その様な特性を持たせることは非常に難しい。それにもしも再生機が録音機とあまりにも違う特性があるとすると、レコードの寿命を相当に縮める可能性がある。電気再生ではその様な障害は起きない。
古いアコースティック録音のレコードの再生を考えるとこの議論はもっと重要である。周波数応答はとてもフラットとは言えないし、時代毎に特性がだいぶん違う。このような古いレコードの再生には、電気録音とは違った特性を持つ再生機が必要となる。
幸運にも、再生機の特性を変えるにはサウンド・ボックスを取り替えればよい。蓄音機愛好家は、昔から古いレコードの音楽の種類によってチューンされたサウンド・ボックスを持っていた。ただし、最近まではチューンの正確な機能が理解されてはいなかったのだが。が電気吹き込みにおいても、初期のものは録音機器がよく分かっていなかったために、それぞれチューンされたサウンド・ボックスを使うことはメリットがある。周波数帯域を狭くする方が、広くするチューニングよりずっと簡単である。バイオリン用にチューンしたサウンド・ボックスは広帯域のオーケストラ再生には全く向かないだろう。ピアノ用の特別なサウンド・ボックスはいつでも有利である。それはピアノの音はトランジェントが大切だからである。
4.
Sound-Boxes
Essential
Features
Motion of a
Diaphragm
The
Air-chamber
Action of the
Stylus-bar
The Electrical
Analogy
Stylus-bar
Mountings
Back-plate and
Gaskets
Miscellaneous
Attachments
Appendix.-Example
of Sound-box Design
はじめに
第四章は再生システムのフロントエンドとなるサウンド・ボックスについてです。サウンド・ボックスはリプロデューサーとも呼ばれ、針の振動を空気振動に変換する役目を担っています。レコードに彫り込まれた波形の溝を針でなぞって、その振動をダイヤフラムという丸く薄い板に伝えます。このダイヤフラムの振動を空気振動に変え、これがホーンに到達して、部屋の空間全体に広がっていきます。一見単純な仕掛けですが、まともな音を出そうとすると、意外と簡単ではなかったのです。そこには機械工学、電気回路などを応用した科学の分析力が必要でした。機械であるサウンド・ボックスの開発に、電気回路解析の応用が必要だったことは大変面白い事実です。機械式の蓄音機の進歩に真空管や電気回路の経験が必要だったことは、LPレコード再生品質の向上にCDの登場が必要だったことと似ているかも知れません。また録音スタジオには次世代のシステムが採用されると、その再生能力の改良に拍車がかかるということでしょうか。
バック・プレートとガスケット
今までの説明では、サウンドボックスのバック・プレートの材料物質、形や重さは、振動の伝達に関係ないものと、意図的にしてきた。このことは、厳密には、バック・プレートが堅く、非常に大きな弾力性(原注 コンプライアンスではない。)と質量のあるときのみ成立する。実用上はこの質量は4から5オンス位が限界である。しかし、これでも、可聴レンジ以上の影響を取り除くのは本当に十分である。材料としては、真鍮やより堅いダイキャスト合金の一種を使用する。サウンドボックスによっては、アルミやエボナイトのバックがある。これらは物質の多孔性により、いくらかの吸音特性がある。サウンドボックスの、どこかに欠陥がある場合は、この特性も有利なこともあるだろう。しかしよく設計され、うまく組み立てられているサウンドボックスでは、ほとんど許されないことだ。
ある種のサウンドボックスでは、シェルが一体(ワンピース)で作られているものがあって、ダイヤフラムは前方から挿入する。この方法だと、いくらかは安く製造でき、組み立て中にダイヤフラムが傷つかないようにすることは、それほど難しくない。しかしながら著者たちは、2つの部品で作られている(ツーピース)サウンドボックスのほうがよいと思う。スタイラス・バーはフロントリムに取り付けられ、バック・プレートは3本の小さなねじでとめられる。この組み立て方法にはいくつかの利点がある。
1.バック・プレートを取り付ける前に、スタイラス・バーとダイヤフラムはフロントリム内に取り付けられる(ガスケットなしで)。ダイヤフラムがエッジとフロントリムの間に同じ間隔で、完全に均一に置かれていることを確認することが出来る。
2.ガスケットを使用するとき、(フロントガスケットは注意深く前から入れる)、バック・プレートはねじで留められるとき、ダイヤフラムにはひずみがかからない。多くの市販のサウンドボックスではダイヤフラム部分の組み立てがひどくて、マイカでは中央にクラックが入っていたり、メタルその他の材質では、捻じれたり、変形したりしている。疑いのないことだが、組み立てがひどいと、せっかく効果のある、その他の点では優れたデザインも、台無しである。
3.3本のねじで取り付けるとガスケットへの圧力が外周全周にわたってよく均一化する。マイカでは、この歪を防止する効果は、サウンドボックスを傾けて、マイカのダイヤフラム上のいくつかの異なった点の光の反射を観察することで分かる。どんな歪でも光の反射の変化で見て取れる。
4.2つのソフトラバーワッシャーを(たとえばガスケット用のゴムチューブ)を3本のねじ毎に使用し、一個はねじの頭とバック・プレートの間に金属かファイバーワッシャーで分け、もう一個は、バック・プレートとフロントリムの間に入れる。再生音質調整に効果的に使用できる。コンプライアンスがバック・プレートとガスケット、ガスケットとフロントリムの間に導入される。これは2つの効果がある。ダイヤフラムエッジのコンプライアンスが増加し、理論的に完全な結果を得るには、大変役に立つ。それ故、ダイヤフラムの動きはピストンのようになり、低音の周波数応答が増加する。同時に、空気室のコンプライアンスにシリーズ要素となる。そこで、コンプライアンスの減少と空気室の深さの増加によって正しい値が得られる。今、空気室の深さを増すことが非常に必要である、それは空気室全体の圧力をより平均化し、出口の端から端での圧力変化の位相を合わせる可能性が高い。その上、バック・プレートとフロントリムとは直接金属接触していないので、振動がトーンアームやホーン金属伝達して伝わったりしない。しかしながら、バック・プレートとフロントリムの間にワッシャーを使うことには、ひとつの危険がある。それは空気室のリークである。これは著しい低音フィルターとなる。この危険は避けることが出来る。それには、バック・プレートにほんの少し持ち上がった部分を作り、それがバックガスケットの周囲に当たるようにすると同時に、ガスケット側面を少し圧縮するようにする。このほんの少々側面方向に圧縮することには利点がある。ダイヤフラムエッジのコンプライアンスを増すことを助けるからである。この目的に合うバック・プレートの形は図32に示した。
今までに説明したことから、ガスケットはサウンドボックスで重要な役目をしていることが分かるだろう。ゴムが材料として最も優れていることはあまねく知られている。それは主にコンプライアンスがとても大きいからだが。欠点は、光、熱、空気の環境変化によって、品質の劣化が速いことだ。ゴム製のガスケットは少なくとも1年に1回は新しいものに取り替えなければならない。前記(4)にあるように、再調整されたサウンドボックスの性能を最高に保ちたければ、それよりも多く交換が必要である。これはガスケットの品質による。あるガスケットのゴムは品質が大変悪く、すぐに弾性を失う。またあるものは大変長く品質を保つ。著者の好きな方法は外形3ミリ、内径1ミリのゴム管形のガスケットをサウンド・ボックスのフロントリムにはめたときにギャップが開いたり、きつかったりしない長さにカットして使うことである。サウンドボックスに組み込むガスケットはただ空気が漏れないということだ。ガスケットは長くても短くても問題がある。フロントリムのサイズはクリアランスをダイヤフラムの全周で1.5ミリになるようにすること。きちんとガスケットの中心をダイヤフラムと合わせることである。
H.M.V.の2番と4番のサウンドボックスでは、連続スプリットリングを使用している。このリングは組み立て前にダイヤフラムに取り付けておける。取り付け後は、ダイヤフラムのエッジは他のどの部品にも接触しない。このリングは組み立てコストを下げることに疑いはない。しかし著者の経験では、きちんと取り付けられたゴム管形(パイプ形)ガスケットほど満足の行くものではない。5番では、ダイヤフラムの周辺にタンジェンシャル形のコルゲーションをつけ、ガスケットにはフェルトを採用した。この方式は、エッジに適当なコンプライアンスを与え、しかもゴムが劣化するような面倒は起きない
5.
Horns
Function of the
Horn
Properties required of a
Horn
Contour of a
Horn
The Exponential or
Logarithmic Horn
Another
Approximation
Size of Mouth
Opening
Non-circular
Section
Folded
Horns
Bifurcated
Horns
Material of
Horns
ホーンの機能
長い間,蓄音機におけるホーンの役割はあいまいにされていた.ある連中は拡声器だと言い,またある者は共振器だという.共振器であれば,自然周波数(基本共振周波数)の音がたまたま出た場合に強調される.しかし,音域の中である特定の音が強調されるのは避けるべきことではないだろうか. これ以前の章で,物事を見るのに2つの見方があることを示してきた.1つには,ホーンはサウンドボックスの空気室とともに働き,ダイヤフラムの負荷となる.それゆえ,ダイヤフラムの共振を目立たなくさせると同時にレコードからのエネルギーを最大限に引き出す.この点から見て,ホーンにとって重要なことは帯域の下から上まで一定の負荷となることだ.そしてホーン自身が共振しないようにしなければならない.
別の面から見ると,ホーンの役目はサウンドボックスが持つ周波数フィルタのインピーダンスを終端する役目である.であるから,必要な周波数帯域の間は純抵抗として動作しなければならない.
上記の2つの見方が実際には同じことの表現であることを理解するのはそれほど難しくない.一定の負荷であることは定抵抗ということになる.共振はリアクタンス成分である.この要求を完全に満たす導管は,一定の太さの長いチューブで,実際には伝声管のようなものである.チューブの壁面がしっかりとしていれば,純抵抗で,定抵抗が得られる.
しかしながら蓄音機においては,もう少し別の要素が必要である.負荷効果のあるチューブ内で作った音を外部の空間に伝達するにあたり,その過程では出来るだけひずみのないようにしたいのである.いま,小口径のチューブの開口端で,音波はほとんど反射して戻る.開口端から問題なく外部に出られるのは高い周波数で,波長がチューブの口径と比較して大きくないものである(原注:波長×周波数=音速).チューブの開口端で反射があるということは,共鳴ができるということである.低域で聞こえる音は,すべての伝送する音の中で,たまたま共振した周波数の音だけである.この開口端での現象をより詳しく説明するのはHannaとSlepianが1924年,米電気技師協会で発表した論文に勝るものはない.
半波長で正圧力の音波がチューブの中を進んでいるとする.チューブ内を進んでいるときは,一様に閉じ込められていて,定容積である.それゆえ,圧力と速度は一定になっている.開口端から離れる際は,しかしながら,第1図のように,大体球形に広がっていく.それで音波が占める容積が大きくなる.明らかに,圧力は下がる.チューブのすぐ外側の圧力がチューブ内より低ければ,チューブのすぐ内側の音速は上がる.すると,すぐ後方の圧力が下がり,音速が上がると,チューブを逆向きに伝達する音波が出来ることになる.それが,開口部の近くで,次にくる音波の圧力を下げ速度を上げる.
反射波は外部の空気に伝わる出力を下げるだけでなく,ダイヤフラムに戻ったときの位相によって,共鳴したり吸収したりする.明らかに反射が少なければ,共鳴,吸収は目立たなくなる. チューブの開口端のサイズが反射の強度にどう影響するか見ることは,簡単である.第1図から,チューブの断面積が大きければ,半波長がチューブの少し内側と,少し外側で占める体積の増加は少ない.それで,反射が少なくなることは明らかである.チューブの直径より波長が短ければ,(第2図)ちょうどチューブを通った後の体積の増加はほんの少しである.だから,反射は無視できるほどである.しかし,波長がチューブの直径より大きければ(第1図),体積の増加は無視できず,反射はかなりのものとなる.
ホーンに必要な特性
さて,ここまできてホーンの必要なことを3つ上げてみよう.
●1 のど(入口)は小さくて,サウンドボックスの出口に合わせる
●2 開口部は大きくして,外部の空気からの反射がほとんどない状態にする
●3 そのために,定負荷,つまり純抵抗とする.
このことから,3つの要求事項は結局矛盾することとなってしまうことを理解することは,それほど難しくない.小面積ののどから相当大きな開口部につなげるためにチューブにはテーパをつけなければならない.だから音波は横方向に広がるようにすることになる.低音は高音より広がり方が大きい.この横方向の拡散で,音圧と音速の位相がずれてきて,ダイヤフラムへの負荷効果を減らす.すでに説明してきたことだが,負荷はいつでも伝達しているパワー(出力)に比例する.電気で出力は起電力(ボルト)に電流(アンペア)をかけたものだが,同様に今扱っている問題では,ホーンのどの部分を通過するパワーは圧力と速度との積である. もし二者の位相がずれていれば出力は減ってしまう.実際,この出力は最大圧力と最大速度の積にパワーファクタと知られている係数を掛けたものに等しい.二者の位相のずれをある角度のコサインで表す.二者が同相であれば,角度は0度で,パワー係数は1である.もし二者が完全に位相がずれていれば,角度は90度で,パワー係数は0で,意味するところはパワーの伝達はまったくないということになる.
前述の議論から,開口部に向かってのホーンの広がり方をゆっくりとすれば,音域に対して負荷はより一様となる.そのためには,開口部はとても大きく,長さもとても長いホーンを作るべきである.
6.
Tone-Arms
Record Groove
Characteristics
Geometrical
Requirements
Acoustical
Requirements
Mechanical
Considerations
Tone-arm
Material
Carrying-arms for
Electric Pick-ups
レコード溝の特性
トーンアームの機能はサウンドボックスをレコード盤の上に運ぶことと、サウンドボックスとホーンとをつなぐことである。その設計方法は、三種類の異なる観点から学ぶことが出来る。つまり、幾何形状、音響効果と機械構造の観点である。最初は幾何的要件を考察し、サウンドボックスがレコード盤上を動くときに正しい方向を向いているかを確かめてみよう。次にトーンアームは単なる音波を伝える管として見てみよう。最後に機械的構造がレコード再生と磨耗へどう影響するかを調べてみよう。
レコードを製造するとき、ワックスの母型が針の下で定速度で回転している。機械的な振動が針に伝えられてないとすると、針はワックス上に単純な渦巻き状の溝を刻む。この渦はギリシャの哲学者の名に因んで、アルキメデスの渦巻きと言う。それは、彼が渦巻きの性質を研究したからである。この渦巻きはレコード溝の平均線を表す事になる。針の振動はサインカーブを渦巻きの線を中心として刻んでいくからである。一般に渦巻きの渦は半径方向にインチ辺り100本である。それを我々は、蓄音機レコードは「インチ100本の溝」を持つと言っている.それで隣り合った溝の間隔は1/100インチである。溝自体が、この距離の半分を占めているので、隣り合った溝へ中央から動ける距離は1/200インチしかない。この意味するところは、隣の溝に食い込まない振幅はたった1/400インチということである。第二章で説明したように、低音を目一杯入れる難しさの理由である。
7. Record Wear, Needles, Surface
Noises
Frictional
Wear
Reactive
Wear
Needles
Surface-noise
レコードの磨耗
レコード製造の初期においては、溝側面の磨耗に悩まされた。そこでレコードには積極的に、研磨剤を入れてレコード針の方を削る作戦に出たのである。しかし、この磨耗の原因の一つは材料の不均一性にもあった。1922年にコロンビアレコードでは、材料を細かく均一にすることで、「新プロセス」レコードを発表した。1929年時点で、事実上磨耗の問題はなくなった。それは、レコードの滑らかさだけではなく、針の硬さや針圧、接触方法が寄与していると考えられる。録音時にはサファイア針を使用し、しかも垂直に立っているのに、最盛時にはそれよりも先端が太く、60度ほど後傾している場合の問題は、針の先端が溝の底面に接触せず、しかも側面で支えられていることである。それで側面が削れるのだが、溝が曲がっているので当たる面が変わることになる。針圧に関しては、筆者たちは5から5.5オンスを勧めている。4オンス以下でも、7オンス以上でも問題がある。溝が削れる他の要素は、アライメンと不良と、側方圧力の存在である。磨耗を避けるために、先の細い鉄針やファイバー針を使うことだが、コンプライアンスが大きいのでサウンドボックスの設計も合わせないといけないし、先が細いためにホルダーを必要とする場合スタイラスバーが重くなり、サウンドボックスのバランスが狂うということにもなる。
再生針
音響的な見地から、蓄音機の針において重要なことは、長さとコンプライアンスである。第四章で説明したが、針先のコンプライアンスとダイヤフラムや空気室等のインピーダンスと整合させるにはニードル・アーム・トランスが必要である。針の長さとマスは、スタイラスバーの部分であると考えなければならない。どのサウンド・ボックスの設計でも、針の長さ、マス、コンプライアンスは互いに関係がある。同じタイプの針でも、サウンドボックスが違うと合わないことがあるだろう。実験で幾つかの針を試すことによって、応答をコントロールする方法を探ることができるようになる。
サウンドボックスのチューニングを完全にするには、スタイラスバーのマス、アッパーアームのコンプライアンス、チャンバーの深さ、ホーンにつながる出口の径を調整する必要がある。それから針のコンプライアンスにも注意が必要である。理論から、コンプライアンスは針の柄にあるのではなく針先にあること事が分った。つまり、最高の設計は殆どの部分は硬く、針先のみが柔軟のものだと思う。この条件を概ね満足するのは槍形のタングスタイル針とファイバー針である。全体が柔らかい針だとしなうので、再生音にもレコードの磨耗にも悪い影響を与える。針先のみにコンプライアンスを集中する方法の唯一の不都合な点は針先が壊れ易くなることだ。タングスタイル針は金属の鞘にタングステンのワイヤが飛び出ている構造である。だから、不注意に扱うと曲がってしまうのだ。
ファイバー針の先端が壊れ易いのはよく知られているが、専用のサウンドボックスで正しく使われれば、耐えられる以上の力がかかっているように見えても、ずいぶんと長く持つのだ。そしてこのような条件下では、ご存知だろうが、再生音は大変質が高い。忘れてならないことは、どの針でも使っているサウンドボックスがすべての特性をコントロールしていることだ。反対に、針の種類は特性の一部のみに影響するのだ。
機械的な観点から蓄音機の針の基本要件は、第一にレコード溝の底にちょうど着く太さであり、第二にはレコード素材よりも柔らかいか出来るだけ硬くて必要なコンプライアンスを一定に与え続けられるものである。買ってきた針のケースには、必ず幾つか悪い針先のものが混じっている。英国の蓄音機針メーカーでは、あるパーセント抜き出して、投影機で映し、基準以下であれば全てのロットを廃棄している。全数検査は彼らの考えにはないのだ。それは毎週何百万本の針が売られているからだ。それ故、針を使う前には灯りの下で針先を検査するのがよいだろう。蓄音機愛好家には、箱を買う毎に拡大鏡の下で針先を全て確認する注意深い者がいる。レコード素材より弱い針は、もちろんレコードに傷が付く前に壊れる。ファイバー針ではこの利点とそれ故の使いにくさがある。
この性質があるので、ファイバー針を専用サウンドボックスで使用すると、レコードの磨耗が機械的条件で起きるのかが判断できる最高の方法となる。トーンアームの動きが悪い、サウンドボックスとトーンアームの接続部のコンプライアンスが大き過ぎる、側面圧の存在、軸のずれたレコード、モーターの回転がギクシャクしている、などの場合、ファイバー針は簡単に壊れる。これらは重要である。この種の針の欠点は、何度か針がつぶれた後、磨耗した破片が溝に詰まることである。それらの破片を放って置くと、今度はそれが針に移って研磨剤の働きをすることになる。もし針がレコード素材よりも硬ければ、なるべく硬いほうがよい。単に細く研磨することが出来るだけではなく、削られて鑿のようになることもない。非常に硬い針では6回の演奏後でも、柔らかい針で一回演奏するよりも磨耗が少ない。だからといって、6回使えるという意味ではない。完璧を期するためにもこれでも一回しか使ってはいけない。特に蓄音機のアライメントが狂っている場合は。針を再度使う場合の問題は、レコードの終わりで削られた面は、レコードの開始点には合わないからである。
8. Electric
Pick-Ups
Functions
Types
Velocity
and Displacement
Devices
Electromagnetic
Pick-ups
Half-Rocker
Moving-Iron Pick-ups
Other
Types
Possible
Developments
Appendix.-Force
Equations of the Half-rocker Pick-up
電磁ピックアップ
電磁ピックアップに可能なデザインは大変多い。ここでは、よく使われている例を説明して一般的な原理を解説することしか出来ない。基本的な特徴は、機械的な動きがコイルを通して磁束を変化させる。この目的を達成するには、磁場の中でコイルを動かすか、磁化したアーマチュアを固定したコイルの中で動かすことで磁束の変化を起こせばよいだろう。最初の方法では、必要なインダクタンス(直径と巻き数で決まる)のあるコイルは重いので、高い周波数での応答が急に悪くなるという問題がある。
その上、レコード針で作動する小さなムービング・コイルをしっかりとした構造で組み上げるのは簡単とは言えないのである。ムービング・コイル・スピーカー(訳注:ダイナミック・スピーカー)の成功を見ると、殆どの実験から、ムービング・アイアン式よりムービング・コイル式方が優れていることを示しているはずだ。しかしムービング・コイル・スピーカーは動きも力もスケールが違うし、誤差もピックアップの場合のように目立つことはない。ムービング・コイル・ピックアップの将来はないと、急いで結論付けるのは早すぎるだろう。しかし、このピックアップはアイアン・アーマチュアタイプよりも大きく高価な磁石、あるいはより軽いコイルで作られることだろう。そうでなければ、特性補償回路網が必要だろう。しかし商業的に成功したデザインはまだ全然出来ていない。
ムービング・アイアンあるいはアーマチュア・タイプでは、コイルはアーマチュアを囲むか、ポール・ピースに巻いてある。The
Round (Marconi), Celestion (Woodroffe), Varley, Brown、H.M.V.
のピックアップは後者のタイプ、Kellogg (B.T.H.), G.E.C. (Hopkins), Phonovox (Igranic), Crosley
Merolaは前者である。
アーマチュアの動作には三種類ある。トランスレーション、ハーフロッカー、フルロッカーである。これらの様々な例は図1にある。すべて、以前に取り上げたKelloggの論文から引用した。以下の長所と短所のまとめはその論文からだが、括弧内には著者達のコメントを加えた。(1)ポール・ピースよりもアーマチュアに線を巻く方がよい。それはアーマチュアでの磁束の変化が多くてもポール・ピースでの磁束変化はほんの少しであるし、その上にコイルを巻いても磁束の全てがコイル全体を横切らないからである。(この議論は出力電圧を出来るだけ大きくすることにのみ興味がある。しかしこれは周波数特性をフラットにすることと比べれば、次善のことである。)
(2)
アーマチュアの左側に2個の磁極を加えること(右側でも同様だが)で同じ動きに対しての磁気効果が二倍になり、(この議論も出力の大きさのみに関心がある。)それはエアー・ギャップが二倍になって、その磁気抵抗が変化するからだ。
(3)
対になった磁極ではさむ事によって、アーマチュアが必ず保持する定常磁束を減らすことが出来、残留磁束あるいは交番磁束のみになる。それ故、この例ではアーマチュアは軽く出来るだろう。(これは周波数応答とレコードの磨耗の両方にとって、重要な考察である。)
(4)
ロッカー・タイプのアーマチュアは、両端が同方向に動くトランスレーション・タイプよりも有利である。磁極に対向した端のみが動くので、磁束の変化を起こすのに効果的である。トランスレーションタイプでは、部品の全体が均等に動くが、ロッカータイプでは中央部は端部よりも動きが少ない。(これもまた重要な考察である。特定の質量においては、ロッカー・タイプの運動量はトランスレーション・タイプよりずっと少ない。
(5)フルロッカータイプのアーマチュアの中央点は定磁位点となる。アーマチュアを2つに切って、上半分を取り除くとしよう。もし定磁位の中央に下半分の動く部分を置いておく限り、フルロッカーで上半分が起こす磁束変化と同じくらいの変化が得られる。言い換えれば、フルロッカータイプでは、上半分の動きは磁束を変化させ、下半分の動きは定磁位の中央にいるために必要と言えるだろう。ハーフロッカータイプではアーマチュアのピボット支軸端部は、動く方の端部に比較してエアギャップの磁気抵抗を低くすることで、定磁位に近い状態に置くことが出来る。
9.
Loud-Speakers
General
Principles
Reed-driven
Mechanisms
Moving-coil
Mechanisms
Diaphragm
Effects
Large
Diaphragms
The
Outlook
ダイヤフラムの効果
第四章で述べたことだが、比較的効率がよく、応答特性を一定にするには、ダイヤフラムは大きな剛性・質量比があり、面積が大きくなければならない。さらにエッジが、できるだけ自由に動け、両面の空気が混ざらないことが必要である。このようにすれば、ダイヤフラムは重要な周波数帯域に渡ってピストン運動をし、共振点をその帯域の上に持っていける。ダイヤフラムの直径が50mmを超えないようにしていれば、コルゲートを付けてもコーン型にしてもアルミのダイヤフラムを使うことで、剛性と質量の条件を満足するのは簡単である。最近のサウンド・ボックスでは前者のコルゲートを使用しているが、Brownの受話器とラウドスピーカーでは、後者のコーン型を使用している。ダイヤフラムをホーンと接続するときは、各条件を満足するのに、特に大きな問題は起きない。しかし、対応する蓄音機のデザインの機械インピーダンスに合わせたものは現れていない。
ラウドスピーカーと大型の指数カーブ・ホーンを組み合わせた大変面白い例は、Movietoneにある。AT&TのためにE.
C. Wente と A. L.
Thurasが特にデザインしたものは、ムービング・コイルでドライブしている。ダイヤフラムをホーンに接続する方法は、図9にある。凹面のダイヤフラムを使用し、ホーンの喉は円形に広がってダイヤフラムのエッジに合っている。このようにして、圧力の変化はダイヤフラムの中央側からでも外側からでも、ホーンの喉に届くが、相当に高い周波数までほぼ位相が合っているのだ。
ダイヤフラムはアルミ製で厚み0.002インチ(40ミクロン)である。外周エッジはタンジェンシャルになっていて、コンプライアンスが高い。ムービング・コイルは外周エッジに近いところに取り付けてあり、一層のアルミ・リボンで0.015インチ幅、0.002インチ厚でエッジ巻きである。コイルは絶縁ラッカーのフィルムで固定してある。このユニットを14フィート以上の長さの指数カーブホーンにつなぐと、周波数応答も60から7,000サイクルまでほぼフラットな応答が得られる。また電気的入力対機械的音響出力の効率も比較的高い。
10. Electric
Amplifiers
Thermionic
Valves
Valve
Characteristics
Intervalve
Couplings
The Output
Stage
Special Conditions for
Reception of
Broadcasting
Low-Frequency
Amplifier Design
Volume
Controls
Mains Units or
Battery
Elimiators
Appendix.-Design
of Amplifier Units
低周波アンプの設計
低周波アンプで、50から5,000サイクルまでのフラットな増幅をするための秘密は、バルブの選択、段間結合用部品の選択、配線・部品・バルブなどの浮遊容量が問題とならないように注意することである。浮遊容量を考慮すると、使えないバルブもある。
バルブ内、バルブ・ホルダー、配線、部品に浮遊容量がある。A.L.M.SowerbyがこのことをWireless
World誌(1928年の2月と3月号)ですばらしい解説をしている。そこで、このコンデンサーが集まってアノード・フィラメント間の大きなコンデンサーになっているとして、初段の出力回路のインピーダンスを等価回路で考える。
註:RC電圧増幅回路において、前段のプレート抵抗をRA、パスコンをK、次段のグリッド抵抗をRG、球や配線からの浮遊容量をまとめてCとしている。
この回路網で、もしRGがRAより相当に大きければ、以下のようになる:
(1) 高音域では(K とRGを無視できる)
(2) 中音域では (CとK は無視できる)
(3) 低音域では (C は無視できる)
また、中音域がフラットとすると、高域での低下と低域での低下を計算できるようになる。
これらの式により分かることは、もし限界周波数である32と8,000サイクルでの低下を5%以下とすることをよい特性標準と考えると(以下、式による解析が続くので中略)
トランス結合の場合は、アンプのデザイナーはトランスの性能を超えることはできない。だから、次段のバルブと組み合わせた周波数特性が保証されているタイプを選ぶことが重要だ。できれば国立物理研究所の認定があるとよいだろう。前段のバルブの動作インピーダンスは20,000オームを超えてはいけないし、電流が多すぎて鉄芯が飽和することがないようにすべきである。よいトランスであっても、ほとんどは3mAを越えられないが、少しは大丈夫なものもある。この章の3項にあるトランスの特性図の上のカーブは、そのようなトランスの特性を示している。周波数が5,000台の高域では若干盛り上がっているのが分かるだろう。これは前述したRC結合での配線などから来る浮遊容量による高域信号の結合によるのだが、この少しの特性の上昇は明らかに有利な点と認められるだろう。
(中略)
バルブ特性の直線部分だけで動作させる重要性についてはすでに述べた。もしバルブを正しく選べば最終段以前では普通何も問題はない。しかし最終段では危険が実際にある。99%のラジオセットではオーバーロードが常に起きていることが言えるだろう。このオーバーロードを避けるためには高圧電源の端子にミリアンペア計を入れることが必要である。この方法の図は付録に示した。バルブの動作がリニアな範囲内であればミリアンペア計の読みは安定している。グリッド・バイアスが小さすぎると、プラスの振幅が下側の曲がりに到達する前に、特性の上側の曲がりを超えるだろう。すると、プラスの振れの間のアノード電流の増加は比例しないので、ミリアンペア計の読みは時々減るようになり、針は目盛り上を下方向に揺れるだ。一方、グリッド・バイアスが大きすぎれば、マイナスの半サイクルの振れの間電流は減る。そしてミリアンペア計に現れる平均電流は時々増えるので、針は上方向に揺れるのだ。グリッド・バイアスが適正だが、過大入力がグリッドに加わっているときは、針は平均値の上下で振れて見える。バイアスがこの適正値に調整されると、最大出力を得ることができるのである。そうしたら、ボリュームを調節して、大パッセージでも針が動かなくなるようにすべきである。
電灯線式電源装置、あるいは無電池式電源(バッテリー・エリミネーター)
放送の初期時代に使用されたバルブと設計の関係で、低圧電池の電流消費が大きく、高圧電池の電流消費はごく少なかった。バルブのデザインが発達して立場は逆転した。すなわち低圧電池の電流消費は少なく、高圧電池の電流消費は多くなったのである。
ごく最近、パワーの出るアンプと、深い低音の出るラウドスピーカーの開発によって、ある変化が現れている。前段の方では、低圧、高圧の両バッテリーで低消費電流のバルブを使うことは可能であるが、終段では数年前まで考えられなかった電圧電流が必要となっている。そのために電流供給を電灯線から取る方法を開発することに向かってきた。よい電灯線式電源装置の初期コストは大変に高いが、大電流を使っても運転コストは蓄電池や電池と比べて大変に低いし、実に便利でもある。現在、電灯線の供給は直流の場合と交流の場合がある。電気式増幅器では、絶対に交流が便利である。交流であればトランスを使用して電圧を上げたり下げたりできるので、高圧用にも低圧用にも使えるのである。その上、交流の供給はおおむね安定であるが、直流ではひどく不安定であることが多い。時には、安定させることが不可能な場合もあるくらいである。いずれにしろ、手に入る電圧には限りがある。モータージェネレータを使えば、直流を交流にするときは標準電圧にするのがよいだろう。そうすれば、高圧を家の中に引き廻す必要がなく、アンプ筐体内のトランスの近くに置くことができるからである。
これらの理由により、近いうちに直流供給が交流供給になるだろうから、我々は交流電灯用電流から直接に変換する機械について考えてみよう。低圧電流について、最も簡単な(著者たちの意見ではベストな)方法は、交流点火のできるバルブを使用することである。普通電池で動作させるバルブを交流を使うと、電灯線周波数のハムを起こすことが多い。この原理の例外は、出力段にスーパー・パワー・バルブを使うことである。このバルブのフィラメントは0.25アンペア以上を消費する。これらのバルブはフィラメントが厚く、交流を使うことに問題はない。他の段では特別なバルブが用意されている。以前説明したのだが、カソードが間接的にフィラメントからの輻射で暖められるものや、低電圧高電流でカソードの役目をするフィラメントを直接に暖める。しかしながら直熱管をアノード・ベンド検波に使うときにはハムを消すのは大変である。それで、どの場合であっても間接加熱バルブ(訳注:傍熱管)を使うのがよいだろう。いずれのケースでも、電灯線電圧はトランスを使って必要な低い電圧となる。負の高圧と正のグリッド・バイアスはトランス二次側(低電圧)にセンター・タップを立てるか、両極に400オームのポテンショメーターを入れることで得られる。(後略)
11. Miscellaneous
Hints
Practical
Considerations
Motors
Parts
of a Spring Motor
Care of the
Motor
Electric
Motors
Speed
Regulation
Levelling the
Gramophone
Record
Faults
Record Strage and
Indexing
モーターの保守
グラモフォン・モーターを使用するに当たっては、以下のルールを覚えておこう。
1. ゼンマイを巻く最中にモーターを回転させたままにしておくこと。しかし、全部巻き上げるまではサウンドボックスをレコードに乗せてはいけない。再生中に巻いてもいけない。
2. 巻き上げるときに一定の力と速度で巻こう。がたがたとした巻き方をしてはいけない。ほとんど巻き上がったら、ゆっくりと回し巻きすぎてゼンマイを外さないように気をつける。
3. モーターが何枚レコードをかけられるかを知っておこう。次の面がかからないと分かっている場合を除き、聞き終わるごとに巻くのは止めよう。聞き終わるごとに数回ハンドルを回すのには反対しないが、ゼンマイの全体を使うように努め、最後の部分だけとか、中間くらいまでという使い方は避けたい。こうすれば、調子を保てる。
4. ターンテーブルがスタートするときに、指で縁を押して助けるようなことはしないこと。柔らかいガバナーのバネを傷めるからである。同様に、レコードの最後でブレーキを急にかけるのも避けたい。モーターを指でやさしく止めてからブレーキをかける習慣をつけるとよい。
5. モーターを全部、あるいは半分巻き上げた状態で放置してはいけない。聴き終わった後は、モーターを回して、ゼンマイをすべてほどいておいて、ハンドルを数回回しておくとよいだろう。もっとよい方法は、モーターの出すノイズを聴いてゼンマイが最後になる直前を知り、そこで止めることである。
6. 三ヶ月に一回とか、モーターに定期的に給油をする。スピンドル・ベアリングとガバナー・シャフトに最高級の軽油を使うのだ。ターンテーブル下のスピンドルのベアリングも忘れずに。ギアにもざらつかないグリースやワセリンを使う。ウォーム・ギアには液体オイルは使用しないこと。ここではざらつかないグリースを使わなければならない。パッドのあたるガバナー・ディスクは完全にきれいにしなければならない。ここに塵やごみがつくと、回転がおかしくなるからである。少しガソリンを染み込ませた布で丁寧に拭き、きれいな軽油を一滴パッドに落とす。パッドがフェルト製であれば、時々硬くなってないか点検をする。表面がてかてかになったら、替え時である。
7. 自動停止装置で、特に動きにがたのあるものはガバナー・スプリングを傷めがちである。使わないようにするのがよい。
8. ターンテーブルを押し込むのは避けたい。スピンドルが簡単に痛み、一度でも起きるとモーターは定速で回らなくなる。
速度調節
モーターの速度はガバナー・パッドとディスクとの距離で行う。パッドは曲がっているレバー上にあり、反対側には速度コントロールと目盛りにつながっている。H.M.V.のモーターでは、独立した小さなブレーキ・パッドがガバナー・ディスクにあって速度インジケーターのポインターをコントロールするものがある。もちろん、どちらのインジケーターでも、実際の速度を示すのはきちんと設定してからだ。実際のモーターの速度を測定するにはいくつかの方法がある。もっとも単純な方法は、細く切った紙片をターンテーブル上に置き端から飛び出すようにし、その上にレコードを置いて再生するのだ。紙片が回転するのを手元に置いた時計で一分間測るのである。ゼロから(1ではなく)数えて秒針が一回転するまでである。それから速度インジケーターを修整するか、毎分78と80回転をする場所にマークをするとよいだろう。
H.M.V.もコロンビアも簡単に速度を測定するテスターを出している。どちらも遠心力で動く錘を利用している。このテスターは掃除をして油を注していれば、精度もまあまあである。
電灯線が交流の人は、非常に正確なストロボ式速度テスターを厚紙で作ることができる。白熱電球は交流のために二倍の周波数で明るさが変化する。これはマイナスの電流でもプラスの電流と同じだけの熱が発生するからである。だから、50サイクルの電気では1/100の時間毎に短い時間消えているのである。もし図3のように白黒の縞模様を円板に描いて、ターンテーブルの中心に置くと、この縞模様が止まったり、ターンテーブルの回転方向に動いたり、またその反対に動いたりする。これはターンテーブルの回転数と縞模様の数によるのである。いま77の同じ大きさの白黒の縞があって、電灯線の周波数が50サイクルであるとする。縞が動かないのは毎分78回転のときである。理由は、一つの黒の縞が1/100秒後に隣の黒の位置まで動くからである。(註:毎分78回転=毎秒1.3回転。1.3×77=100.1)このような簡単な計算で78あるいは80回転で停止する縞の数を、下に示した表のように出すことができる。
(表は略す 周波数は25から60サイクルまでである。)
この方法では、モーターが安定に回転しているかどうかが一目で分かる。それはどんな速度の変化もストロボのパターンにすぐ現れるからである。電灯線周波数は50サイクルに統一されるので、レコードラベルに印刷するのがよいのではないだろうか。
 TOPへ戻る
TOPへ戻る
 HOMEへ戻る
HOMEへ戻る


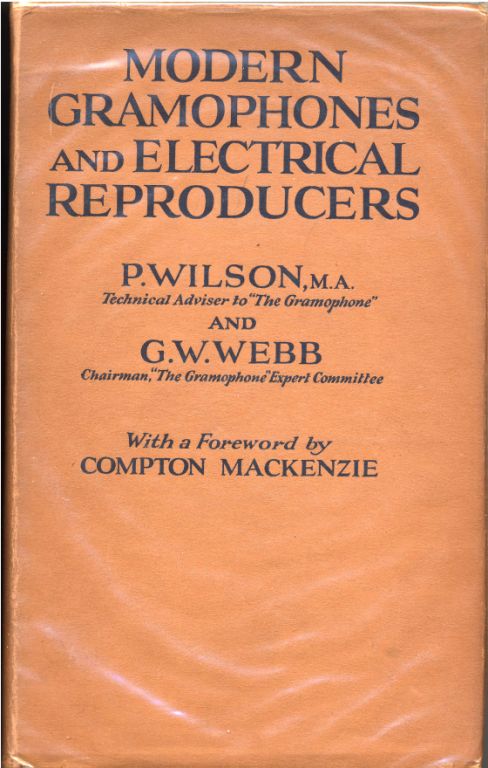 1929年に英国で出版された、「Modern Gramophones and Electrical
Reproducers」の目次と、その内容を少しずつ紹介します。
1929年に英国で出版された、「Modern Gramophones and Electrical
Reproducers」の目次と、その内容を少しずつ紹介します。